 企業を経営していると必ず直面するのが、「労災保険」と「雇用保険」です。
何となく日々使っている用語ではありますが、深堀りしてみると、非常に興味深い内容となっています。
また、この二つの保険は、「労働保険」と総称され、一体的に扱われることもあります。
今回は、この「労災保険」と「雇用保険」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。
企業を経営していると必ず直面するのが、「労災保険」と「雇用保険」です。
何となく日々使っている用語ではありますが、深堀りしてみると、非常に興味深い内容となっています。
また、この二つの保険は、「労働保険」と総称され、一体的に扱われることもあります。
今回は、この「労災保険」と「雇用保険」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。
「労働保険」とは
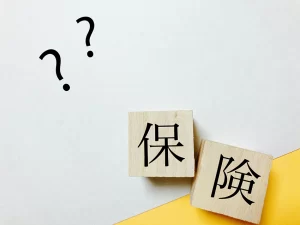
「労働保険」とは
「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律という法律があり、この中で定義されています。 また、給付はそれぞれの保険で別個に行われているのですが、保険料の納付などは、一体で取り扱われています。
(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
「労働保険」入らなきゃダメ?
「労働保険」は、労働者を一人でも雇用していれば適用事業に該当します。 労働者には、パート・アルバイトが含まれます。 適用事業になる事業主は、加入手続を行い、労働保険料を納付することが必要になります。「労災保険」と「雇用保険」の違い
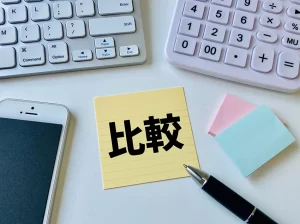 労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付がなされる制度です。
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため、失業者や教育訓練受ける方等に対して、失業等給付を支給する制度です。
したがって、雇用継続中の労働災害での傷病の場合の「労災保険」と、失業や育児介護休業の場合の「雇用保険」という整理ができることになります。
労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付がなされる制度です。
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため、失業者や教育訓練受ける方等に対して、失業等給付を支給する制度です。
したがって、雇用継続中の労働災害での傷病の場合の「労災保険」と、失業や育児介護休業の場合の「雇用保険」という整理ができることになります。
「労災保険」とは

労災保険とは
労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付がなされる制度です。 また、受傷・疾病にかかった労働者の社会復帰促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保を図ることも目的としています。 この労災保険は、政府が管掌しており、労働者を使用する全事業が適用事業となっています(公営や、小規模事業についての例外有)。 費用は、政府が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により事業主から徴収される保険料によってまかなわれます。 ここでは、主に給付について説明します。労災保険で受給できる給付

療養補償給付
これは、いわゆる治療関係費用です。 診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養に必要な費用が給付されます。 療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すると、請求書が、医療機関から労働基準監督署長に提出されますので、療養費を支払う必要はなくなります。 療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。医療機関への支払いの後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働者から労働基準監督署長に提出し、その費用が労働者に支払われることになります。休業補償給付
これは、給与の代わりになるものとイメージできます。 労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。 「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。障害補償給付
残念ながら、労災によって後遺障害が残ってしまった場合には、認定された等級に応じて、一定額の年金または一時金が支給されます。遺族補償給付
不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。葬祭給付
葬祭料が支給されます。傷病補償年金
休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。 ただし、労基署長の職権によることになっています。後遺障害について
労災における後遺障害等級は、当事務所の次のページも参照してください。 https://www.g-rosai.jp/cms/shogaitokyuhyo/「雇用保険」とは

雇用保険とは
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため、失業者や教育訓練受ける方等に対して、失業等給付を支給する制度です。 また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための事業も行っています。 この雇用保険は、労働者を使用する全事業が適用事業となっています(小規模事業についての例外有)。 雇用保険料は、事業主と従業員の双方が負担します。 ここでは、主に給付について説明します。雇用保険で受給できる給付
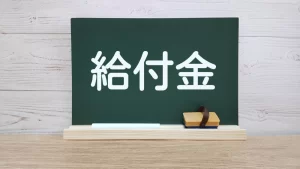
求職者給付
一般被保険者は、次の手当を受給できるのが原則です。 ●基本手当 基本手当は、ハローワークに提出する離職票に基づき計算しますが、給与の総支給額(保険料等控除前。賞与除く)により、概ね以下のとおりとされています。 ①平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度 ②平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度 ③平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度 ※離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合は、別途の計算 概ね、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率で計算されますが、 給付額には上限・下限があることに注意が必要です。 雇用保険の基本手当には、受給資格があります。 離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要とされていますが、倒産・解雇等の理由により離職した場合や、更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要とされています。 また、当然ですが、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある場合にのみ支給されます。 厚生労働省のHPによれば、失業の状態とは、 ・積極的に就職しようとする意思があること。 ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。 ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。 とされていますので、育児や病気、ケガですぐに就職できないなどの場合には、受給できません。 ●その他の手当 技能習得手当、寄宿手当、傷病手当(雇用保険(基本手当)の受給手続後に病気やけがのため15日以上職業に就くことができない状態になった場合に、雇用保険(基本手当)と同額の支給を受けることができる手当)などを受けることができる場合があります。就職促進給付
就業促進手当としては、次のようなものがあります。 ●再就職手当 再就職手当は、基本手当の受給資格がある労働者が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当する場合に支給されます。 計算式は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)。 ●就業手当 就業手当は、基本手当の受給資格がある労働者であって、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件に該当する場合に支給されます。 計算式は、就業日×30%×基本手当日額(上限あり)。 ●常用就職支度手当 常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある労働者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある労働者など、就職が困難な労働者が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されるものです。 ●移転費 受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等の場合で、住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者と家族の移転に要する費用が支給されるものです。 ●その他 広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費などの支給もあります。教育訓練給付
働く人々の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される、教育訓練給付制度によって支給されるものです。雇用継続給付
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「介護休業給付」が支給される制度です。「労災保険」と「雇用保険」の違い・まとめ

労働災害と、失業や育児介護休業という適用場面の違い
今まで見てきましたように、雇用継続中の労働災害での傷病の場合は「労災保険」が適用になり、失業や育児介護休業の場合は「雇用保険」が適用になります。加入すべき労働者の違い
事業所としては、労働保険、すなわち、労災保険も雇用保険もいずれも加入しなければいけません。 そして、労働者の観点では、労災保険は、すべての労働者が加入する必要がありますが、雇用保険は、加入すべき労働者については一定の条件があります。 なお、加入手続きは、事業所が行う必要があります。 すなわち、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出し、その年度分の概算労働保険料を申告・納付します。 詳しくは、厚生労働省のHPをご参照ください。 厚生労働省:労働保険の成立手続 (mhlw.go.jp)保険料の負担の違い
労災保険は、すべて事業所が保険料を負担します。 雇用保険の場合は、事業所と労働者とが保険料を負担しますが、負担率は、保険料率によって定められます。 なお、労災保険料の計算方法は、賃金総額×労災保険料率で計算します。 くわしい労災保険料率は、厚生労働省のHPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html また、雇用保険料の計算方法は、賃金総額×雇用保険料率で計算します。 くわしい雇用保険料率は、厚生労働省のHPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html労災の事故防止義務と事故時の補償責任
事業主は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たし、労災事故を防止する義務を負っています。 違反がある場合には、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。 また、労災事故が発生した場合、事業主は労働基準法により補償責任を負いますが、労災保険に加入している場合には労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。他方、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。 なお、通常は労働基準法上の補償責任だけでは労働者に生じた損害はカバーできないので、労災での支給に不足する部分については、当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などを根拠に民事上の責任追及(損害賠償請求)がされることもあります。 そして、労働災害が発生したにもかかわらず、労働災害を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがありますので注意が必要です。労災事件とグリーンリーフ法律事務所







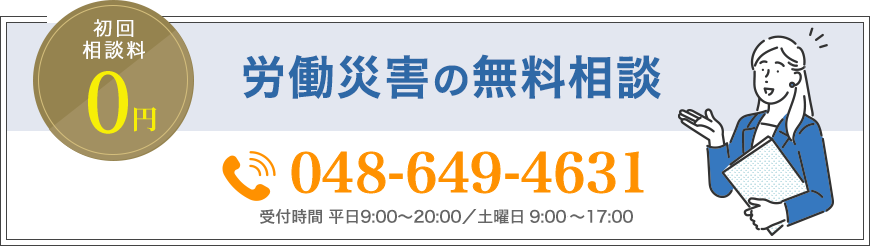
66 レビュー